「ささのはさーらさらー♪」と童謡の『たなばたさま』は、昔から親しまれている名曲ですよね。
しかし改めて歌ってみると、歌詞の意味がわからない。

「のきばに揺れるー♪」の、のきばって何?

「きんぎんすなごー♪」の、すなごって何?
ふと歌っていて疑問に思ったので、のきば・すなごについて調べてみました。
映像が浮かぶとより楽しめますよね。
子どもにも教えることが出来ます。
歌詞の意味と、たなばたさまの歌詞、七夕行事、七夕の由来についてまとめました。
童謡たなばたさまの歌詞に出てくる「のきば」と「すなご」とは!?
のきば・すなごって今は馴染みのない言葉ですよね。
それぞれ絵も使って解説していきます。
のきばって何?
「のきば」は漢字で「軒端」と書きます。
軒端とは漢字の通り、軒(のき)の端(はし)っこです。
軒(のき)とは屋根が建物の壁から出てる部分です。

軒端で、笹の葉がさらさら風に揺られてる様子を歌ってるんですね。
風情がありますね。
すなごって何?
「すなご」とは漢字で『砂子』と書きます。
砂子(すなご)とは金銀の箔を粉にしたものです。
金箔や銀箔を細かく砂のようにしたもので、襖(ふすま)とか色紙とかにたまに付いているキラキラ光るものです。
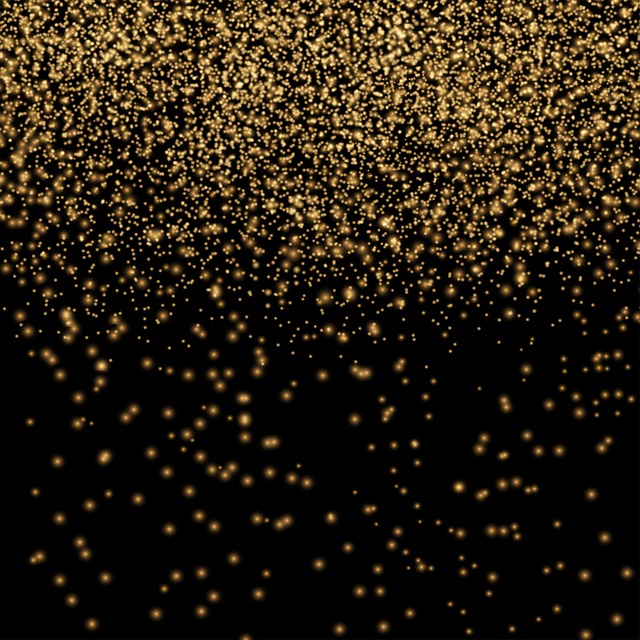
空に光る星がキラキラ光って砂子のように見えると歌ったのでしょうか。
それとも短冊に砂子が使われていて、風でゆらゆら揺れている短冊が砂子のようにきらきらと光っているのかもしれません。
改めてたなばたさまの歌詞をみてみよう!
題名が、『七夕』『ささのはさらさら』と勘違いすることがありますが
正式には『たなばたさま』という題名です。
作詞:権藤はなよ 補作詞:林柳波
作曲:下総皖一
ささの葉さらさら
のきばにゆれる
お星さまきらきら
きんぎん砂子
・・・・・・・・・・・・
五しきのたんざく
わたしがかいた
お星さまきらきら
空からみてる
歌詞を知って歌ってみると、より映像が浮かんできますよね。
願いを叶えてくれるような気持になってきます。
七夕はいつ何をする行事?七夕に食べる食べ物は?
七夕は「たなばた」と読むのが一般的ですが、「しちせき」とも読みます。
昔から行われてる日本のお祭りの行事です。
1年間の重要な節句の、5節句のうちの1つです。
毎年7月7日の夜に、願い事を書いた色のついた短冊と飾りを、笹の葉につるして、星にお祈りをする日です。
織姫(おりひめ)さまと彦星(ひこぼし)さまが、天の川を渡って、1年間に1度だけ出会える夜でもあります。
7月7日はそうめんを食べると1年間無病息災で過ごせると言われています。
北海道や宮城県仙台市など、8月7日に七夕を行う地域もあります。
七夕の由来は?
七夕の由来は諸説ありますが、3つの事が合わさって出来た行事と考えられています。
3つの七夕の由来
①日本の神事「棚機(たなばた)」が由来
②織姫様と彦星様の伝説が由来
③中国から伝わった行事「乞巧奠(きこうでん)」が由来
それぞれ解説していきます。
①日本の神事「棚機(たなばた)」が由来
棚機(たなばた)は、若い女の子が着物を織って棚に供えて、神様を迎え秋の豊作を祈り、人々のけがれをはらうという、日本の禊(みそぎ)行事でした。
選ばれた若い女の子は棚機女(たなばたつめ)と呼ばれます。
棚機女は、川などの清い水辺にある機屋(はたや)にこもって、神様の為に着物を織ります。
その時、着物を織るために使うのが、棚機(たなばた)という織り機です。
のちに仏教が伝わると、この行事はお盆を迎える準備として7月7日の夜に行われるようになりました。
棚機(たなばた)の当て字で、七夕(たなばた)となったと言われています。
②織姫様と彦星様の伝説が由来
こと座のベガと呼ばれる織女(しゅくじょ)星は裁縫の仕事の星。
わし座のアルタイルと呼ばれる牽牛(けんぎゅう)星は農業の仕事の星。
そのように考えられていました。
この2つの星は旧暦の7月7日に天の川を挟んで、最も光り輝いて見えると言われています。
中国ではこの日を1年に1度のめぐり逢いの日と考え、七夕の物語が生まれました。
七夕の物語
七夕の物語には諸説ありますが、、、
昔あるところに、神様の娘である織姫と、若者の彦星がいました。
織姫は機織りの仕事をする働き者。
彦星は牛の世話をしているしっかり者。
やがて2人は結婚しました。
しかし、今まで働き者だった2人は急に遊んで暮らすようになり、働かなくなってしまいました。
怒った神様は、2人の間に天の川を作って離してしまいました。
2人は悲しみ、泣き続けました。
それを見た神様は、前のようにしっかり働いたら、1年に1度だけ、2人を会わせてくれると約束しました。
それから2人はまた、真面目に働くようになりました。
そして、2人は1年に1度の7月7日だけ、天の川を渡って会うことができます。
その日7月7日が七夕となりました。
③中国から伝わった行事「乞巧奠(きこうでん)」が由来
「乞巧奠(きこうでん)」とは中国の行事です。
7月7日に織女星(しゅくじょせい)にあやかって、機織りや裁縫が上達するようにとお願いすることから始まりました。
庭の祭壇に針などを供えて、星に祈ります。
そのうちに機織りだけではなく、芸事や字が上達することも願うようになりました。
この、日本の棚機、織姫と彦星、乞巧奠の3つが合わさって、今の七夕になったと考えられています。
たなばたさまを歌って七夕をもっと楽しもう!
『たなばたさま』は昔から知っている歌なのに、歌詞の意味を知りませんでした。
歌詞の意味や、七夕行事の由来などを知るとより一層楽しめますよね。
7月7日はぜひ星を見上げながら、『たなばたさま』を歌って、願い事をしてみましょう。



コメント